- Hygiene Shop
- > 麻疹(はしか)のABC
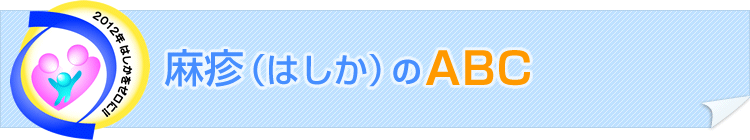

麻疹は麻疹ウイルスによっておこる感染症で、感染力がきわめて強く、麻疹の免疫がない集団に1人の発症者がいたとすると、12~14人が感染するとされています(インフルエンザでは1~2人)。通常は春から初夏にかけて流行しますが、通年発生します。麻疹ウイルスに感染すると10~12日間の潜伏期間の後、2~4日38℃程度の発熱が続き、上気道症状(咳、鼻水、くしゃみなど)、結膜炎症状(結膜充血、目やになど)、倦怠感(小児では不機嫌)が次第に強くなります。その後、39℃以上の高熱とともに発疹が出現し、発疹が全身に広がるまで3~4日間39.5℃以上の高熱が続きます。合併症がない限り7~10日経てば主な症状は回復しますが、免疫力の回復には1ヶ月程度要するといわれており、その間他の感染症にかからないように十分注意する必要があります。
●麻疹の合併症
麻疹に伴って免疫力が低下するため感染症にかかりやすくなり、肺炎、脳炎、中耳炎、心筋炎など様々な合併症がみられます。その約半数は肺炎です。合併症の中で、肺炎と脳炎が麻疹による二大死因となっています。
●10代における麻疹の集団発生
麻疹は乳幼児が罹る疾患というイメージがありますが、麻疹に免疫がなければ10代や成人でも麻疹に感染します。2007年や2008年には、10代における麻疹の集団発生が問題となりました。
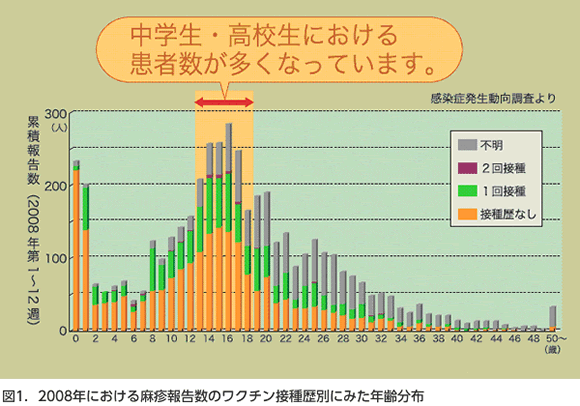
2001年の全国的な麻疹の流行以降、ワクチン接種に対する意識が高まり、1歳早期におけるワクチン接種率が向上し、これまで麻疹の流行の中心であった乳幼児における麻疹は著しく減少し、社会全体で麻疹の流行が抑えられました。しかしその一方、麻疹に対して免疫を持たない人でも麻疹に罹患しないままでいるケースや、過去にワクチンを接種したものの麻疹ウイルスに感染する機会が減ったために自然感染による免疫増強効果を得ることがないまま接種から年数が経ち麻疹に対する免疫が減弱するケースがみられるようになりました。そしてそのようなケースの人が多数存在する可能性の高い学校などにおいて、麻疹ウイルスが入り込み、10代における麻疹の集団発生が起こったと考えられています。
2007年の10代における麻疹の集団発生を受けて、2008年度からは中学1年生相当、高校3年生相当の年齢を対象とした麻疹ワクチンの定期接種が始まりました。その結果、2009年以降10代の麻疹患者数は大幅に減少しています。
●国の麻疹排除のための取り組み
厚生労働省は、「麻しんに関する特定感染症予防指針」で、2012年度までに麻しんを排除することを目標に掲げています。その目標を達成するために、2008年度から、(1)10代における麻疹ワクチンの定期接種の機会設定、(2)麻疹の全数報告対象化、(3)麻疹が地域で発生した場合、直ちに疫学調査を実施して対策を行い、感染拡大の防止に努める、といった3点を取り組みの3本柱としてきました。しかし、2011年では1年間の麻疹患者数が400人を超えており、目標達成が難しい状況です。厚生労働省は、予防指針の5年ごとの見直し時期が迫っていることから予防指針の見直しと改定を検討しています。
●感染症法での取り扱い
麻疹は5類感染症に位置づけられており、全数報告の対象となっています。可能な限り24時間以内に届け出ることが求められています。
●学校保健法での取り扱い
麻疹は、学校において予防すべき伝染病2種に定められており、発症した生徒は熱が下がって3日を経過するまで出席停止となります。発症した人が周囲に感染させる期間は、発疹が出現する3~5日前から発疹出現後4~5日目くらいまでとされています。

麻疹の感染経路は空気感染・飛沫感染・接触感染があります。
表1 麻疹の感染経路
| 空気感染 | 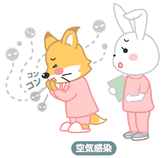 麻疹ウイルスの直径は100~250nmで、飛沫核の状態で空気中を浮遊し、それを吸い込むことによって感染する 麻疹ウイルスの直径は100~250nmで、飛沫核の状態で空気中を浮遊し、それを吸い込むことによって感染する |
| 飛沫感染 | 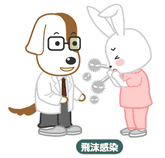 麻疹ウイルスに感染した人の咳やくしゃみなどによって発生する飛沫が飛散し、比較的近距離にいる人がそれを吸い込むことにより感染する 麻疹ウイルスに感染した人の咳やくしゃみなどによって発生する飛沫が飛散し、比較的近距離にいる人がそれを吸い込むことにより感染する |
| 接触感染 | 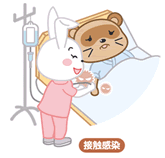 麻疹ウイルスが付着した環境表面などに触れた手指を介して感染する 麻疹ウイルスが付着した環境表面などに触れた手指を介して感染する |
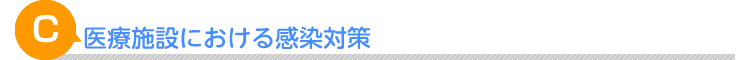
標準予防策に加えて空気感染予防策の実施。
飛沫感染・接触感染の可能性もあるため飛沫感染予防策、接触感染予防策も考慮。
ワクチン接種によって麻疹に対する免疫をあらかじめ獲得しておくことが大切。
●平常時の対策(最も重要)
- すべてのスタッフの麻疹罹患歴と麻疹ワクチン接種歴を記録に基づいて確実に把握しておく。
- 麻疹未罹患かつワクチン未接種あるいは1回接種、または、麻疹抗体価検査により抗体陰性もしくは抗体価が低いと判断された場合にはワクチン接種を勧める。
●患者発生時の対応
麻疹患者の対応にあたるスタッフは、麻疹抗体価検査によりすでに抗体陽性が確認されているか、麻疹に罹患したことがあることが確実な人、麻疹ワクチン接種歴が2回記録で確認されている人に限定します。
外来に麻疹疑いの患者が来た場合は、他の患者と接触しないように別室に隔離し、出来る限り早く診察するように配慮します。
入院患者が麻疹(疑い含む)であることが判明した場合は、麻疹患者を速やかに隔離することはもちろん、感染拡大防止のために麻疹患者と接触した可能性のある患者・スタッフに対しても対策を講じることが重要です(表2)。
表2 入院患者が麻疹(疑い含む)であることが判明した場合の対応
| (1)麻疹患者の隔離 |
|
| (2)麻疹患者の行動調査 |
|
| (3)接触者の調査 |
|
| (4)接触者の対応 |
|
●マスクの必要性
麻疹は空気感染・飛沫感染する疾患のため、麻疹に免疫がないスタッフがやむを得ず患者対応しなければならない場合には本人の防護のためにN95マスクあるいはそれ以上の性能のものを着用すべきです。麻疹に対する免疫があることが確実なスタッフはN95マスク等がなくても対応可能ですが、ほかの疾患に感染する可能性もあるためサージカルマスクの着用が推奨されています。また、外来に麻疹患者が来院した場合や麻疹患者移送時などは、麻疹患者にサージカルマスクを着用させ、咳エチケットを遵守させましょう。
医療機関での麻疹対応ガイドライン(第三版)(平成23年9月25日)
平成23年9月に国立感染症研究所感染症情報センター麻疹対策技術支援チームにより作成されたガイドラインで、医療機関のスタッフ(実習生含む)、外来・入院患者における麻疹の感染・発症を予防することを目的としています。本ガイドラインでは、スタッフの平常時の対応、院内で麻疹(疑いを含む)患者発生時の外来・病棟での対応、麻疹患者発生状況の継続的な把握と疫学調査ついて記載されています。麻疹患者発生時は、患者の対応にあたるスタッフは麻疹抗体陽性が確認されている人または麻疹含有ワクチンの2回接種が記録により確認されている人に限定し、迅速に麻疹患者の隔離・発症予防策の検討を行うように示されています。また、麻疹患者の行動調査を行い、他の患者・スタッフなどの接触者を把握し、必要に応じて接触者に発症予防策を実施するように示されています。
●麻疹ウイルスに有効な消毒法
麻疹ウイルスはエンベロープを持つウイルスのため、消毒薬は比較的効きやすく、高水準消毒薬、中水準消毒薬、熱水消毒が有効です。また、麻疹ウイルスは空気中や環境表面では生存時間は短い(2時間以下)とされています。
環境整備や手指衛生などではエタノールなどの消毒薬が使いやすく、効果的です。
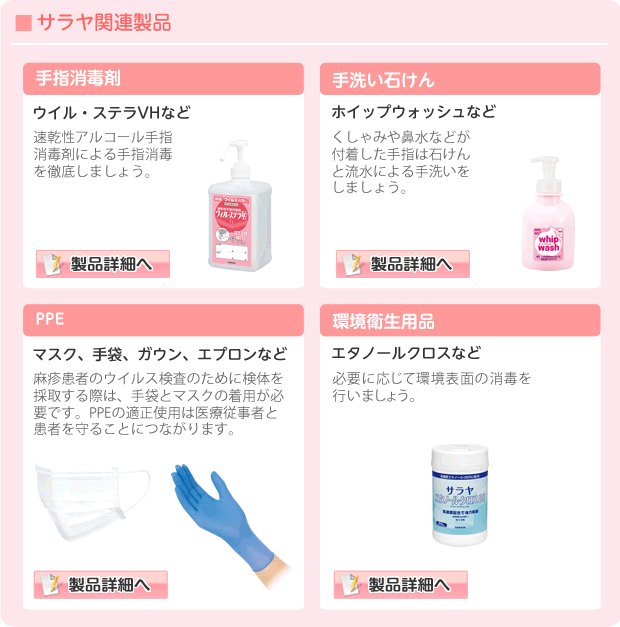
1) 厚生労働省 麻しん(はしか)に関するQ&A
2) 国立感染症研究所感染症情報センター
3) 国立感染症研究所感染症情報センター麻疹対策技術支援チーム.
医療機関での麻疹対応ガイドライン(第三版)(平成23年9月25日)
4) 矢野邦夫 他 訳・編. 改訂2版医療現場における隔離予防のためのCDCガイドライン. メディカ出版 2007.
5) 小林寬伊 編集. [新版]消毒と滅菌ガイドライン. へるす出版 2011.




