- Hygiene Shop
- > 手足口病


手足口病(hand,foot and mouth disease:HFMD)は、口腔粘膜および手や足などに現れる水疱性発疹を主症状とした急性ウイルス感染症です。学童(6歳)以上の年齢層はすでにウイルスの感染(不顕性感染も含む)を受けている場合が多いため、成人での発症は多くなく、例年、報告数の90%前後を5歳以下の乳幼児が占めています。国内における手足口病流行のピークは夏季ですが、秋から冬にかけても多少の発生がみられます。定点報告対象(5類感染症)に分類されているため、指定届出機関(全国約3,000カ所の小児科定点医療機関)は週毎に保健所へ届け出なければなりません。
●2013年の流行状況
2013年第19週(5月6日~5月12日)以降、定点当たりの報告数は増加が続いておりましたが、第31週(7月29日~8月4日)は減少しました(図1)。しかし、過去5年間の同時期と比較して、かなり多い報告数となっているため、今後の動向に注視が必要です。
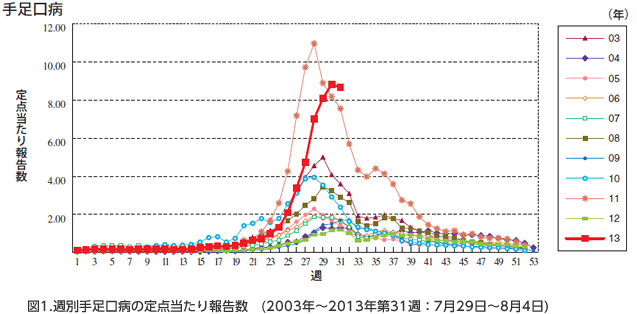
●原因ウイルス
手足口病の主な原因ウイルスはエンテロウイルス属のコクサッキーウイルスA16(CA16)、エンテロウイルス71(EV71)ですが、コクサッキーウイルスA6、A9、A10などが原因となることもあります。2013年(第1~31週)に手足口病患者より検出されているウイルスは、2011年に流行したCA6が全体の約66%を占めており、25都道府県から268件報告されています。次いで、中枢神経系の合併症を引き起こす割合の高いEV71が全体の約23%を占めており、18都道府県から94件報告されています(図2)。
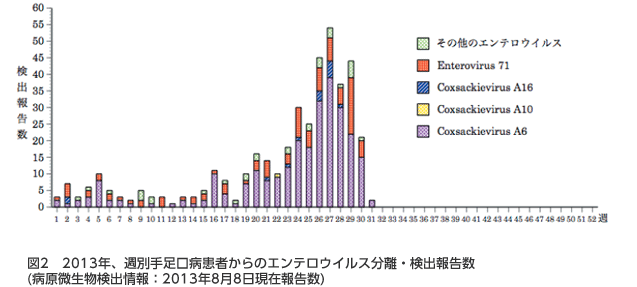
●症状
 3~5日の潜伏期をおいて口腔粘膜および手や足などの四肢末端に2~3mmの水疱性発疹が現れます。発熱は約1/3にみられますが軽度で、高熱が出ることは稀です。通常3~7日の経過で水疱が消え、かさぶたを形成することはありません。
しかし元気がない、頭痛、嘔吐、高熱、2日以上続く発熱などがみられる場合には、髄膜炎、脳症などへの進展に注視する必要があります。
3~5日の潜伏期をおいて口腔粘膜および手や足などの四肢末端に2~3mmの水疱性発疹が現れます。発熱は約1/3にみられますが軽度で、高熱が出ることは稀です。通常3~7日の経過で水疱が消え、かさぶたを形成することはありません。
しかし元気がない、頭痛、嘔吐、高熱、2日以上続く発熱などがみられる場合には、髄膜炎、脳症などへの進展に注視する必要があります。

感染経路は咽頭から排出されるウイルスによる飛沫感染、便中に排出されたウイルスによる経口感染、水泡からの接触感染などがあります。
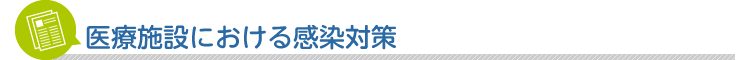
予防は手洗いのなどの衛生管理をしっかりと行うなど、標準予防策の徹底が基本となります。施設での集団感染の制御の際や、オムツをしている小児、便失禁がある小児に対して罹患期間中は接触予防策を行います。
便中のウイルス排出期間は長期間続き、症状が消失した後も2~4週間にわたり感染源になる可能性があるため、排泄物は適切に処理する必要があります。
また、手足口病の原因となるエンテロウイルスは消毒薬抵抗性が高いノンエンベロープウイルスであり、消毒には次亜塩素酸ナトリウムもしくは高水準消毒が有効です。

【参考】
- 1) 国立感染症研究所;IDWR感染症週報2013年第31週
- 2) 国立感染症研究所;警報・注意報発生システム
- 3) 厚生労働省;手足口病に関するQ&A
- 4) 日本病院薬剤師会編集; 消毒薬の使用指針 第3版 , 34 , 1999
- 5) 矢野邦夫, 他 訳・編. 改訂2版医療現場における隔離予防のためのCDCガイドライン. メディカ出版 2007.




